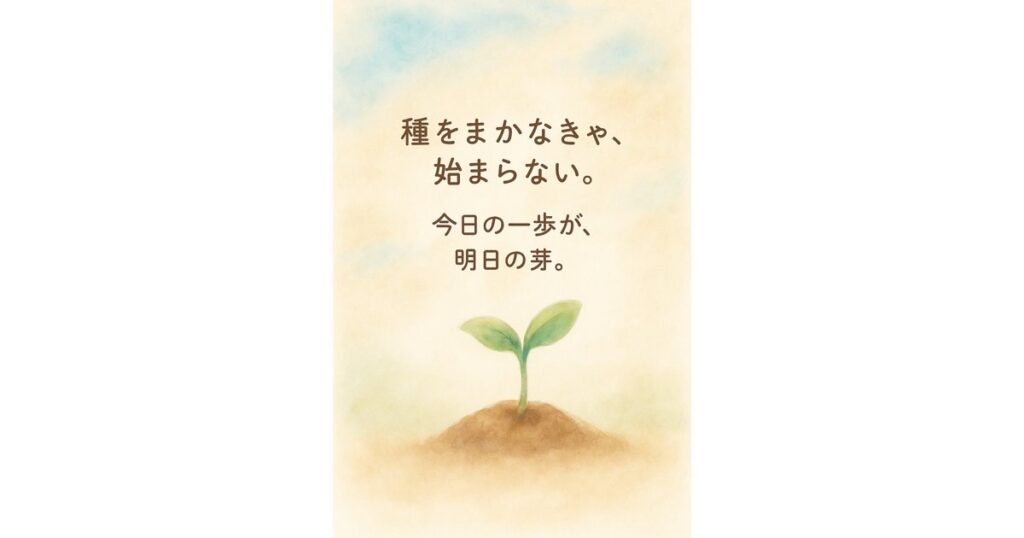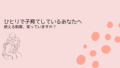ひとり親家庭を支えるために「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の4つの柱で、さまざまなサポートが行われています。
今回は4つ目の「経済的支援策」について説明します。
経済的支援策にはどんなものがあるの?
経済的支援策には、現金が直接もらえる・税金が安くなる・お金を貸してもらえる、という子育てや生活に直接関係のある様々な給付金、手当、貸付金、減税制度があります。
経済的支援策:お金の給付・控除・貸付
- 児童扶養手当
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
- ひとり親家庭住宅手当(自治体による)
- 児童育成手当(主に東京都など一部の自治体)
- ひとり親控除(税金が安くなる制度)
これらは、全国で共通して利用できるものと、お住まいの地域(自治体)によって制度があるもの・ないものがあります。
医療費助成のように、日々の出費を減らしてくれる制度は「子育て・生活支援策」で紹介しています。▶「子育て・生活支援策」
1.児童扶養手当
ひとり親家庭の子どもの生活の安定と自立をサポートするために、国からもらえる手当です。
対象者
・離婚や死別などで父または母のどちらかと暮らしていない子ども
・親の生死がわからない(行方不明)、親に障害がある子ども
・基本は18歳までの子ども(障害がある場合は20歳未満)
※学年でいうと高校卒業の年度末までもらえます。
支給額(月額)
令和6年度の支給額(令和7年1月支給分から)
・子ども1人の場合: 全額支給で45,500円、一部支給で10,740円~45,490円。
・子ども2人目にプラスされる額: 10,750円。
・児童3人目以降1人につきプラスされる額: 6,450円。
所得制限
親の所得や扶養親族の人数によって、全額支給、一部支給、不支給のいずれかになります。
これは令和6年11月分(令和7年1月支給)から引き上げられました。
・全部支給の所得上限額(年収ベース・子ども1人の場合):160万円から190万円へ。
・一部支給の上限額(年収ベース・子ども1人の場合):365万円から385万円へ。
※所得が上がって手当の受給対象から外れた場合でも、一部の就労支援事業では1年間をめどに支援を継続できるようです。
支給時期
年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
前々月と前月の2か月分の合計額が支給されます。
支給日は原則として11日です。
これまで公的年金を受給できる場合は児童扶養手当が支給されませんでしたが、年金額が手当額を下回る場合は、その差額分の手当を受けとれるようになりました。
原則として受給資格取得から5年または支給要件に該当して7年が過ぎて、就業が難しい事情がないにも関わらず働く意欲が見られない場合は、手当が2分の1に減る場合もあるので、注意が必要です。
2.母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭の親や寡婦(※)が、生活や子育てに必要なお金を無利子または低利で借りられる制度です。
※「寡婦(かふ)」とは、夫と死別した女性のことを指します。
対象者
子どもを育てている母子家庭の母、父子家庭の父(平成26年10月1日より対象拡大)、寡婦などが対象です。
12種類の資金項目
資金は目的ごとに12種類あり、学費、資格取得費、生活費、引っ越し費用、結婚資金など、幅広い内容がカバーされています。
子どもの教育に使える資金
- 修学資金(高校・大学などの授業料・交通費)
- 就学支度資金(受験料・制服代など)
- 修業資金(子どもが就職のために通う訓練など)
- 結婚資金(結婚のための準備費用)
親の仕事・生活を支える資金
- 技能習得資金(資格やスキルのための学費)
- 就職支度資金(通勤用の服や道具の購入など)
- 生活資金(就職活動中や資格取得中の生活費)
その他の生活支援資金
- 医療介護資金
- 住宅資金(購入・改築など)
- 転宅資金(引っ越し費用)
- 事業開始資金(起業時の設備費など)
- 事業継続資金(事業の運転資金など)
資金の種類や連帯保証人の有無によって、無利子または年利1.0%での貸付です。
また、条件によっては返さなくていい場合(返済免除)もあります。
たとえば:
入学準備金・就職準備金は取得した資格を活かして5年間働いた場合
住宅支援資金は1年間働いた場合
3.ひとり親家庭住宅手当
自治体によって家賃の一部に対して補助を受けられる制度があります。
引っ越し費用の一部を補助するものもあるようです。
対象者
18歳または20歳未満の子どもを育てている人
支給額
自治体によって異なりますが、平均で5,000円~10,000円が相場のようです。
たとえば:
東京都世田谷区で月額最大4万円
東京都国立市で家賃の3分の1(月額1万円まで)
兵庫県神戸市で月額最大1万5千円 など
所得制限
多くの自治体で児童扶養手当の所得制限限度額に合せているようですが、具体的な金額は市区町村によって異なります。
支給時期
具体的な時期は市区町村によって異なります。
4.児童育成手当
東京都など一部の自治体が独自に実施している手当です。
対象者
東京都内に住所があって、一定の状況にある18歳までの子ども(学年でいうと高校卒業の年度末までの子)を育てている保護者
・母親が結婚せずに出産した子ども
・父親または母親が重度の障害をもっている子ども
・1年以上、親に育てられていない子ども
・親が亡くなった、または生死がわからない子ども
・親が刑務所や拘置所などに1年以上入っている子ども
・両親の離婚により、父または母と生計を共にしていない子ども
・DV保護命令を受けた子ども などが含まれます。
支給額(子ども一人あたりの月額)
児童1人につき月額13,500円です。
所得制限
申請者の所得制限があります。
支給時期
支給は申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に前月までの分が振り込まれるのが一般的です(東京都の場合
5.ひとり親控除
ひとり親の人が納税するときに受けられる所得控除の一つです。
令和2年分の所得税から適用されています。
対象者
ひとり親に該当する人
控除額
35万円(所得から引かれる金額。税金が安くなる仕組みです。)
頼りになる5つの支援策ですが…
児童育成手当とひとり親家庭住宅手当は、地方自治体や都道府県が独自に実施している制度です。
私の住む雪あり県には、どちらもありませんでした。
制度の有無や内容は地域によって大きく違います。
「うちの地域には何があるかな?」と思ったら、まずは市役所や役場の窓口で聞いてみてくださいね。
“知らないと損する”制度、けっこうありますよ◎