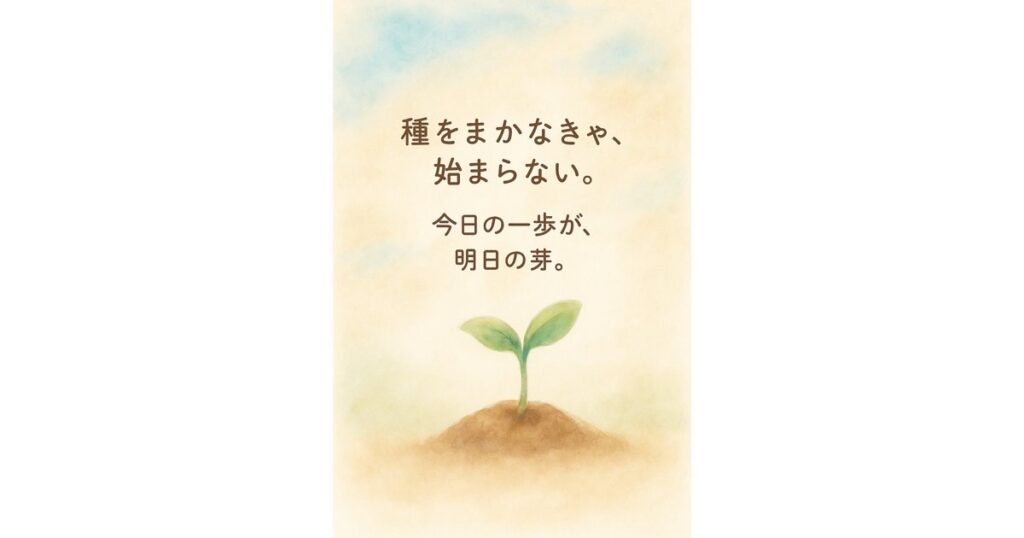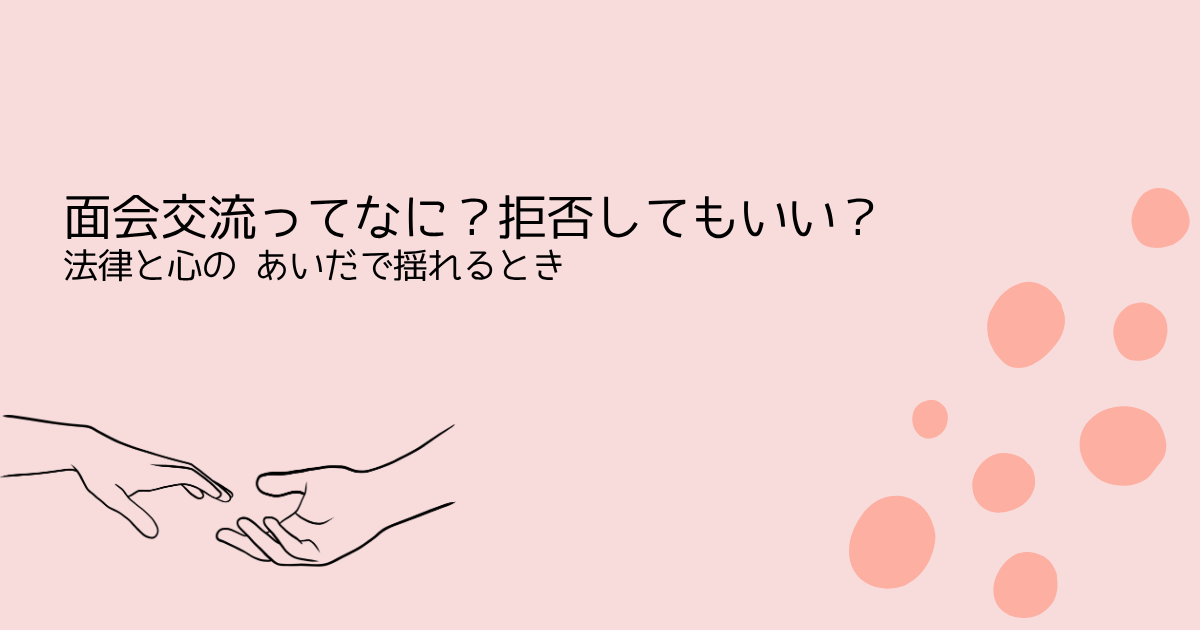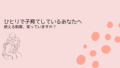前回お伝えした「親権」と同じくらい、離婚や子育ての場面でよく出てくる大切な言葉が「面会交流」。
今回は、面会交流の基本をわかりやすくお伝えします。
面会交流とは
面会交流(親子交流)とは、離婚または別居した親と子ども、あるいは両親以外の親族が、定期的に会ったり、話をしたり、電話や手紙などで連絡を取り合ったりする交流のことです。
※もとは離れて住む親と子どもの交流を指しましたが、2024年5月民法等改正法が成立した際に両親以外の親族も対象になり、名称も「親子交流」に変わりました。
面会交流の目的は?
「そもそも、どうして“会わせる”ことが必要なの?」と思う方もいますよね。
これは、両親が離婚した後も、子どもの成長に関わり続けることは、子どもが安心して過ごすために、とても大切なことだとされているためです。
そのため、離婚して子どもと一緒に住んでいない(親権を持っていない)ほうの親にも「子どもと会って関わる権利」があります。
どんな内容を取り決めるの?
面会交流の方法・内容に決まったルールはありませんが、子どもの年齢、健康状態、生活状況、親同士の関係性などをよく考えて、子どもに負担をかけないように無理のない範囲で、具体的に決めることが大切です。
面会交流は基本的に子どもが経済的に自立するまで、具体的には成人するまで(2022年改正民法施行後は18歳まで)実施されるとしています。
ただし、子どもが成長してくると、本人の意思が尊重されるようになるため、必ずしも成人まで続くとは限りません。
具体的には以下のような項目を話し合って、書面に残しておくことが勧められています。
面会交流の内容
直接会って話をする、一緒に遊ぶ、宿泊を伴う交流、電話、手紙、メール、SNSでのやり取りを認めるかなども決められます。
面会交流の頻度と時間
月に何回会うか、週に何回程度か、1回につき何時間程度実施するかなどを具体的に決定します。夏休みなどの長期休暇中の宿泊交流についても検討されます。
面会交流の場所
公園や一緒に住んでいない親の自宅など、特定の場所に限定するか、その都度決めるかなど。
子どもの受け渡し方法
どこで、何時に待ち合わせるか、誰が子どもを連れて行くか、迎えに行くか、交通手段、遠方の場合の交通費負担なども具体的に決めます。
プレゼントやお小遣い
渡す場合の金額の制限や、誕生日・クリスマスなどイベント時のみとするかなどを決めます。
高額なものを与えるのは子どもの健全な成長を妨げる可能性があるため、事前にルールを決めることが大切です。
学校行事への参加
入学式、卒業式、運動会、発表会などへの参加の可否を事前に取り決めておきましょう。
連絡手段
普段や緊急時の連絡方法(電話、メール、LINEなど)についても話し合っておいて、一緒に住む親の了承なく子どもと直接連絡を取ることは控えるべきです。
その他特記事項
事情が変わった場合の連絡先、約束違反時の取り決めなども検討します。
夫婦間で話し合いがまとまらないときは?
子どもにとっていちばん良い形になるように、家庭裁判所が間に入って決めてくれることもあります。
養育費の支払いがない場合でも、面会交流を拒否するのはむずかしい…
養育費を払ってもらえていないと、「なんでそんな相手に子どもを会わせないといけないの…」と思ってしまいますよね。
でも、「養育費の支払い」と「面会交流の実施」は、別のものとして考えられています。
養育費は子どものための権利です。
相手が養育費を支払わないことを理由に、面会交流を拒否することは、原則として正当な理由にはなりません。
なぜなら、面会交流は「親のため」ではなく、子どものための権利だからです。
そのため、養育費の支払いがない場合でも、会うことが子どもにとって問題にならないなら実施されるべきだと判断される可能性が高いわけです。
もし養育費の未払いが悩んでいるときは、面会交流とは別に、養育費の請求調停(または審判)や、強制執行の手続きで解決をめざします。
また、面会交流を続けることで、別に住んでいる親が子どもとのつながりを実感して、養育費の支払いのモチベーションに繋がることもあるといいます。
私が離婚したときの決めごとの1つが「子どもたちの会いたい気持ちは尊重する」ですが、実際のところは離れたばかりの頃は私も年に数回でも会うことがしんどくて仕方なかったです。
今は子どもが会いたいなら会わせてあげればいい、と思うくらいにはなっています。(年3回ほど)
難しい気持ちもあると思いますが、「子どものためにどうするのがいいか」を軸に、でも自分の気持を抑えすぎずに、少しずつ考えていけたらいいですね。
面会交流の実施を拒否できる場合があります。
子どものための権利なので親の都合だけで一方的に拒否することはできないといっても、面会交流を続けることで、子どもが不安を感じたり、心や生活に悪い影響が出ると裁判官に判断されたときは、中止や制限されることがあります。
- 子どもが15歳以上など、ある程度の年齢に達しており、面会交流を明確に拒否している場合。
- 面会交流によって子どもの生活に悪影響が及ぶおそれがある場合(家庭内暴力、不登校など)。
- 一緒に住んでいない親が過去に子どもを連れ去った、またはその危険性がある場合。
- 一緒に住んでいない親に薬物使用の疑いがあるなど、違法行為や問題行為があり、子どもに重大な危害が加えられるおそれがある場合。
- 別居・離婚の原因が一緒に住んでいない親の暴力・DVであり、子どもや一緒に住んでいる親に強い恐怖心や精神的負担が大きい場合。
ただし、これらの場合でもすぐに全ての面会交流が禁止されるのではなく、第三者の立ち会いや手紙・メールなど間接的な交流のみが認められることもあります。
2024年5月の法改正(2026年5月までに施行予定)によって、共同親権の導入や面会交流にちて新たな規定が決まりました。※リンクはる
これらは、子どもの連れ去りの一定の抑止につながり、離婚後も、別々に暮らす親が子どもと関わり続けられる、そんな社会に少しずつ近づいていくことが期待されます。