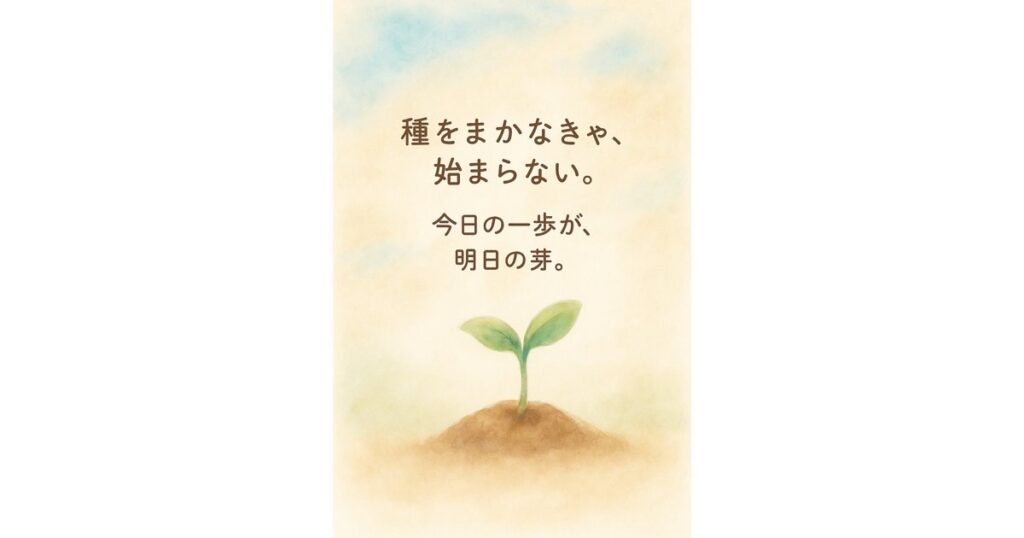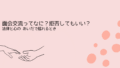離婚や子育ての場面でよく出てくる「親権」という言葉。
なんとなく知っていても、実際どんな内容かは意外と知られていません。
この記事では、親権の基本をわかりやすくお伝えします。
親権(しんけん)とは
親権とは、未成年の子どもが大人になるまで育てて守るための親の権利と責任(義務)のことです。
これらは親の都合ではなく、子どもの幸せをいちばんに考えて使われるべきものです。
親権は大きくわけて2つの内容で構成されています。
親権の「2本の柱」
法律的にはよく「親権は2本の柱でできている」と言われます。
【親権の2本柱まとめ】
| 柱の名前 | 内容 |
| 財産管理権 | 子どもの財産(お金・不動産など)を 親が管理する権利 |
| 身上監護権 | 子どもの生活や教育に関わる・ 育てる責任と権利 |
1本目の柱:子どものお金やものを親がまとめて管理する権利(財産管理権:ざいさんかんりけん)
子ども名義の貯金や物・不動産などを親が管理したり、使ったり、守ったりすることができる権利
【財産管理権でできること(例)】
| 子どもの財産 | 親ができること(財産管理権) |
| 銀行口座・預貯金 | 出し入れ・管理・貯金する |
| お年玉・お小遣い | 必要に応じて管理する(無駄遣い防止とか) |
| 相続で得た財産 | 売却・保管・運用(必要であれば) |
| 不動産(例:祖父母から相続) | 賃貸に出す・売却 (※家庭裁判所の許可が要ることも) |
この管理に含まれること
- 守る(例:通帳や財産を安全に保管する)
- 使う(例:子どもの学費や生活費にあてる)
- 増やす(例:貯金する・ジュニアNISAの運用)
- 代わりに契約する(例:スマホ契約をする、結婚の同意)
ただし、 子どものためだけに使うのが前提!親の生活費にしてはいけません。
また、未成年者は判断能力が未熟と考えられているので、親権者の同意なしで高額な商品を購入した場合など、その契約を取り消すことができます。(同意権・取消権)
2本目の柱:監護・教育する義務(身上監護権:しんじょうかんごけん)
一緒に暮らして、日常の世話や教育をする権利と責任
監護:子どもの身の回りのことを世話すること
=子どもが元気で生活できるようにすること
教育:子どもが社会で生きていくために、必要なことを学ばせること
=子どもが将来困らないように、ちゃんと育ててあげる責任
権利:親が子どもを守り育てるために、できること(していいこと)
義務:親が子どもを守り育てるために、しなくてはいけないこと
「子どもを学校に行かせる」のは、親の自由(権利)でもあり、行かせなくてはいけないこと(義務)でもあります。
身上監護権に含まれる権利と義務は
身上監護権には、以下のような具体的な権利や義務があります。
1.子の人格の尊重等
親権者は子どもの人格を尊重して、年齢や発達の程度に気を配って、子どもの成長に悪い影響を与えるような叱り方や言動はしてはいけない、と法律でも定められています。
これは、いわゆる「しつけ」としての体罰もNGということです。
2022年4月の民法改正により、これまでの「懲戒権」に代わって新しく設定されました。
2.居所指定権
子どもがどこに住むかを決めることができる権利
3.職業許可権
子どもが働くことなどを許可する権利
4.身分行為の代理権
子どもの身分法上の行為に関する親の同意・代理権
子どもが名前を変えたいとか、結婚したいといったときに変わりに同意すること
「未成年の結婚には保護者の同意が必要」と聞いたことが有りませんか?あれです。
親権とは、「親が子どもを好きにできる権利」ではなく、子どもが大人になるまで、安心して育てていくために親が持っている大事な権利なんです。
子どもはまだ社会のことを知らないし、判断がむずかしいこともいっぱいあるからこそ、親がその子の代わりに「どうするのがいちばん良いか」を考えて動く、それが親権の本質です。
離婚したら、親権はどうなる?
現在(2025年7月時点)は、子どもが18歳未満(=未成年)だったら、親権者を1人に決める単独親権というルールがあります。
しかし、2024年5月に改正案が通ったので、今後は離婚しても両親ともが親権を持つ共同親権も選べるようになる予定です。
共同親権については、こちらの記事もどうぞ
▶離婚後の子の養育に関する民法改正 2024年5月成立②
子どもを育てるのはどちらの親か?
現在(2025年7月時点)は、「親権者」を家庭裁判所に届け出する必要があります。
「親権者=子どもを育てる側」と思われがちですが、実際には事情によって異なることもあります。
基本的には両親で話し合って決め、育てる側の親を親権者とするケースが多いようです。
また、どうしても話し合いで決まらないときは家庭裁判所が判断することもあります。
親権者はどうやって決まるの?
親権者(単独にするか、共同にするか)をどう決めるかは、離婚の方法によって異なります。
協議離婚の場合(ふたりで話し合って離婚する場合)
現在(2025年7月時点)は単独親権ですが、今後は両親の話し合いによって、単独親権にするか、共同親権にするかを決めます。
このとき、親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。
話し合いがスムーズにまとまることが、スムーズな離婚手続きにもつながります。
話し合いがまとまらないとき・裁判離婚の場合
話し合いで親権者が決まらない場合や、調停・裁判を経て離婚する場合は、家庭裁判所が最終的に親権者を決めます。
このとき裁判所は、両親と子どもの関係性、子どもを育てるための環境、両親同士の関係などもふまえながら、「子どもが安心して幸せに育てるかどうか(=子どもの利益)」をいちばんに考えて判断します。
また、裁判所は両親それぞれの意見を聞いたうえで、子どもの年齢や発達に応じて子ども本人の意思を汲み取るよう努めます。
共同親権が選べないケースもあります
以下のような場合は、家庭裁判所の判断によって、共同親権は認められず、必ず単独親権となります。
- 両親の一方にDV(身体的・精神的・経済的)や子どもへの虐待があると判断された場合
- 両親の関係が極めて悪く、一緒に親権を行うことが困難と認められた場合
- 共同親権にすることで、かえって子どもの安心や育ちを妨げると判断された場合
このような場合でも、あくまで大切なのは「子どもが安心して育てられる環境かどうか」です。
裁判所も、その子にとって最善の形になるよう丁寧に判断します。
裁判所が親権者を決めるときに判断すること
- 子どもに対する愛情
- 親の収入などの経済力
- 代わりに子どもの面倒を見てくれる人がいるかどうか
- 親の年齢や心身の健康状態などから、子どもの身の回りの世話をする能力があるかどうか
- 住宅事情や学校関係などの生活環境
- 子どもの年齢、性別、発育状況
- 子どもが乳幼児の場合は、母親が親権者として指定されることが多い傾向にあります(母性優先の原則)。
- しかし、実際に育てていけるかはとても大切なところなので、母親だから常に有利というわけではありません。
- 子どもの環境変化が生活に与える影響(継続性の原則)が重視されます。
- 兄弟姉妹が分かれることにならないか(兄弟不分離の原則)
- 不貞行為(浮気など)があったとしても、それだけで親権者として不適切と判断されることは少ないですが、子どもに悪影響を与えた場合は判断材料にされます。
- 別居中に、子どもを世話していない親が無断で子どもを連れ去るなどの行為は、親権者の適格性を判断する上で大きなマイナスとなることがあります。
子ども本人の意思はどう扱われるの?
・裁判所では、15歳以上の子どもの場合は、本人の意思がかなり尊重されます。
・10歳前後でも、判断能力があると認められれば意思が尊重される傾向にあります。
※ただし、その個の年令や状況によって個別に判断されることもあります。
私の場合、元夫氏も私も、子どもたち二人ともを引き取りたいという気持ちが強く、最終的には一人ずつ引き取るというかたちで話し合いが落ち着きました。
一般的には兄弟を分けない「兄弟不分離の原則」が重視されますが、子どもたち自身の気持ちも聞いたうえで決めた、わが家なりの選択です。
原則通りではない選択でも、子どもの気持ちを大切にして出した答えなら、それも立派な「親の判断」だと思います。
結婚しているとき:共同親権
両親が二人で一緒に親権を持ちます。
離婚後(現在):単独親権
両親のうち、どちらか一方だけが親権を持ちます。
離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚届を受け取ってもらえません。
離婚後(民法改正後):共同親権
2024年5月に決まった改正内容では、離婚後も両親で一緒に親権を持つことを選ぶことができるようになります。
※この改正法は2026年5月までに施行される見込みです。
※民法改正についてはこちらの記事をどうぞ
▶離婚後の子の養育に関する民法改正 2024年5月成立①
▶離婚後の子の養育に関する民法改正 2024年5月成立②
親権を持っていないと、子どもに会えなくなる?
安心してください。
「親権がない=会えない」ということはありません!
離れて暮らす親が子どもと会ったり連絡をとったりすることは、「親子交流(以前でいう面会交流権:めんかいこうりゅうけん)」という、親権とは別の権利として認められています。
親子交流についても2024年5月に改正法が決まりました。
まとめ
- 親権とは、「子どもを育てるための責任と権利」のこと
- 離婚するときは、原則としてどちらか一方が親権者になる(=単独親権)
- 親権がなくても、子どもと会ったり関わったりすることはできる!
次回の記事では、親権とは別に認められている「親子交流(旧:面会交流権)」について、詳しく解説します。