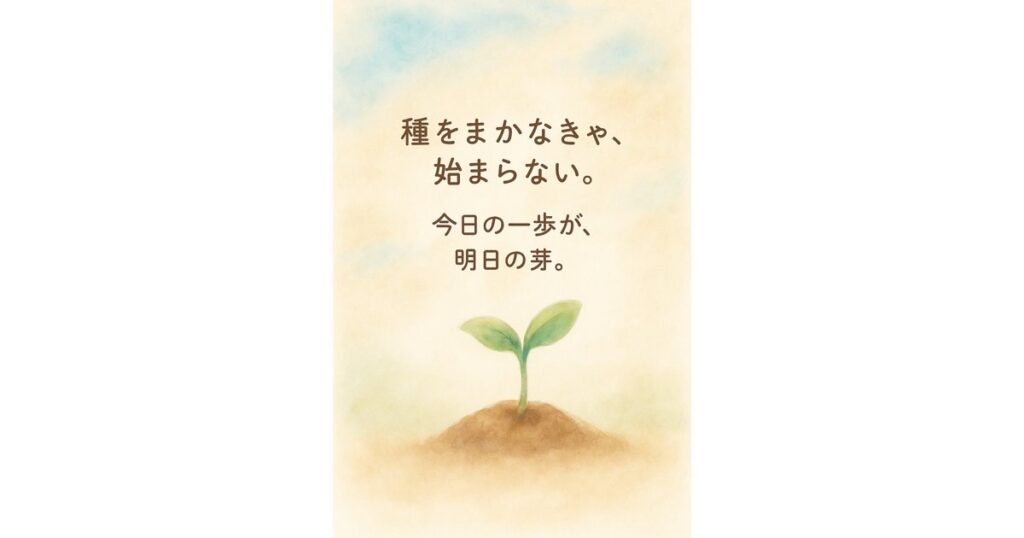この記事は、前回ご紹介した「離婚後の子の養育に関する民法改正(2024年5月成立)①」の【後編】です。
離婚や別居が子どもに与える影響はとても大きく、「子どもが安心して幸せに育つこと」を一番に考えた制度への見直しが進められました。
今回はその中でも、『親子交流』『財産分与』『養子縁組』の3つのポイントを、できるだけやさしい言葉でまとめました。
前編をまだ読んでいない方はこちらからどうぞ👇
▶ 離婚後の子の養育に関する民法改正 2024年5月成立①
制度の見直しで変わったところ
ここでは『親子交流』『財産分与』『養子縁組』の3項目についてまとめました。
親子交流
【今までどうだった】
これまでは、離婚や別居をした親と子どもが「会う」「連絡をとる」といった交流(=面会交流)については取り決めができていましたが、
「結婚しているけど別居している親」や「祖父母など、両親以外の親族」との交流については、法律に特に決まりがありませんでした。
今回の改正で、そういった場合にも、親子交流として家庭裁判所などで取り決めができると明文化されました。
【今回どうなった】
「子どもが安心して幸せに育つことを一番に考える」という考えのもと、
従来の「面会交流」よりも広い意味をもつ「親子交流」という形で、別居中の親だけでなく、祖父母などの親族との関わりも認められるようになりました。
【なぜ変わったのか】
家庭裁判所が「親子交流」について調停や審判をする際は、すべて“子どもの安心と幸せ”を一番に考えて判断することになっています。
実際には、両親が結婚していてもさまざまな理由で子どもと別に暮らすことがありますし、祖父母との関係がとても深い子もいます。
そういったケースでも、離婚後と同じように、家庭裁判所や両親の話し合いによって交流内容を決められるようになりました。
また、祖父母など両親以外の親族についても、「子どもにとって特に必要だ」と判断される場合には、家庭裁判所が交流の実施を命じることもできるようになりました。
一部の親族からは、家庭裁判所に親子交流をお願いする申し立てもできるようになっています。
| 項目 | 旧制度(〜2024年5月) | 新制度(今後 ※2026年5月までに施行予定) |
|---|---|---|
| 呼び方 | 面会交流(めんかいこうりゅう) | 親子交流(おやここうりゅう) |
| 対象 | 主に「離婚後に別居している親と子」 | 両親のどちらかに限らず、祖父母などの親族も対象になることがある |
| 申し立てできる人 | 両親のみ | 両親だけでなく、祖父母など親族も申し立てできるようになる |
| 交流の条件 | 子どもが安心して暮らすことが最優先。内容は調停や裁判で決める。 | 子どもの安心や健やかな育ちのために特に必要と認められた場合に交流ができる |
「親子交流」には、会うことだけでなく、手紙・電話・オンライン通話なども含まれるようになりました。
「祖父母とも会わせたい」と思っても、必ず認められるわけではなくて、あくまで子どもの気持ちや安心が最優先で考えられます。
財産分与
【今までどうだった】
財産分与を請求できる期間は、これまでは離婚後2年以内とされていました。
また、分与の対象となる財産についても、相手に聞いて教えてもらうしかない状況で、「財産なんてないよ」と言われてしまえば、本当はあるはずの財産に気づけないまま終わってしまうケースも多かったようです。
【今回どうなった】
財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年に延長されました。
さらに、家庭裁判所が相手に対して財産の内容を開示するよう命じることができる仕組みも新たに作られました。
これによって、相手の財産を調べられずに泣き寝入りする…という不公平を減らすことが期待されています。
【なぜ変わったのか】
財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年に延長されました。
さらに、家庭裁判所が相手に対して財産の内容を開示するよう命じることができる仕組みも新たに作られました。
これによって、相手の財産を調べられずに泣き寝入りする…という不公平を減らすことが期待されています。
養子縁組
【今までどうだった】
普通養子縁組(いわゆる「養子縁組」)の場合、たとえ育ての親に引き取られても、法律上の親権は生みの親に残ったままという仕組みでした。
そのため、育ての親が子どもの生活に責任を持って関わっていても、病院の同意や学校の手続きなど、法律上の判断は生みの親に頼らざるを得ないケースがありました。
【今回どうなった】
養子縁組がされた場合の親権を誰が持つのかが明確にされて、子どもを実際に育てる人が法律上もちゃんと親として認められるようになりました。
- 一般的な養子縁組された場合:養親がその子供の親権者となり、実親は親権を失います。
- 複数回養子縁組された場合:最後に養子縁組をした者のみが親権者となります。
- いわゆる「連れ子養子」の場合: 再婚した相手と、子どもの実の親(再婚相手の配偶者)が一緒に親権を持つことになります。
養子縁組の手続きにおいて、両親の意見が対立した場合に家庭裁判所が調整するための手続きが新しく作られました。
【なぜ変わったのか】
養子になる子どもが、法的にも親子としてしっかり認められて、“家族の一員”として安心して暮らしていけるようにするためです。
最後に少しだけ、注意点
この法律は2024年5月に成立しましたが、実際に施行されるのは2026年5月ごろの予定です。
今すぐすべての内容が適用されるわけではないことにご注意ください。
今回の法改正は、「親の都合」ではなく「子どもの気持ちや安心」を一番に考えるための見直しです。
離婚や別居があっても、大人たちの関係に子どもが振り回されるのではなく、安心して暮らし、育っていける環境が守られるように――
そんな思いが込められていることが、今回いろいろ調べてよくわかりました。
制度はまだこれから施行される段階ですが、“知っている”というだけでも、大切な選択ができる場面があると思います。
どなたかの安心につながるきっかけになれば嬉しいです。