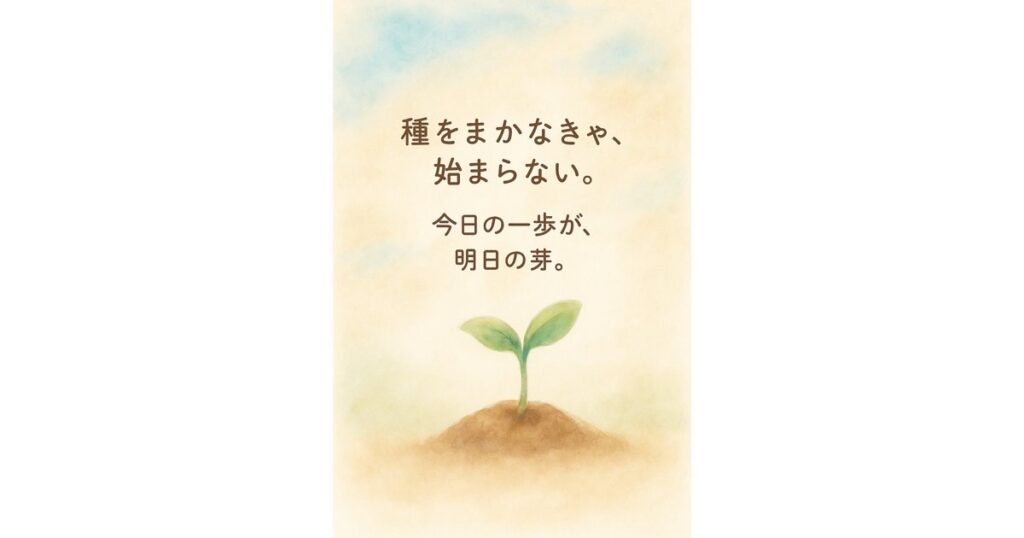2024年5月に離婚後の子どもに関わる民法の改正が行われたことを知っていますか?
私が離婚したのは約3年前なのでこのことは全く知らず、今回ブログを書くためにいろいろな情報を探している中で知りました。
子どもに関わるとても大切な内容だと感じたので、多くの方に知ってもらいたくて、法律のむずかしい言葉をできるだけやさしくまとめました。
ぜひお時間のあるときにでも目を通してみてください。
離婚は、親にとっても大きな出来事ですが、子どもにとっても同じように大きな出来事です。
今回の改正では、『親の義務と責任』『親権』『養育費』『親子交流』『財産分与』『養子縁組』の主な項目について、”子どもが安心して幸せに育つこと”を一番に考えた見直しが行われました。
そのため、今までのルールを変更しただけでなく、新しい仕組みも作られました。
制度の見直しで変わったところ
ここでは『親の義務と責任』『親権』『養育費』の3項目についてまとめました。
親の責務(義務と責任)
【今までどうだった】
これまでの民法では、「子どもを育てていく親の義務と責任」があいまいな部分も多く、法律の中で明確には書かれていませんでした。
【今回どうなった】
今回の改定では、両親が結婚していたかどうか、親権者なのかどうかに関わらず、両親共子どもを育てていく義務と責任を持つことが決められました。
【なぜ変わったのか】
子どもが安心して幸せに育つことを考えて、両親は離婚しても「子どもを育てていく仲間」として、子どものために協力することが必要、との考えからです。
- 子どもが心も体も元気に育っていけること(子どもの健全な成長)
- 一人の人としてちゃんと向き合うこと(子どもの人格の尊重)
- 気持ちを大事にしてあげること(子どもの人格の尊重)
- 子どもの気持ちに寄り添って支えること(心理的なサポート)
- 生活に困らないように経済的に支えること(養育費などお金の支援もふくむ)
これらの考え方は、これまでも「当たり前のこと」とされてきましたが、今回の改正で『父母間の人格尊重・協力義務』(※)として、法律の中に明確に書かれる(=明文化される)ことになりました。
これにより、両親が協力して子どもを支える姿勢が、よりはっきりと求められるようになります。
※父母間の人格尊重・協力義務:お互いの意見を尊重しつつ、誠実に話し合って協力する義務
これらに該当する場合、裁判所が親権者の指定や変更をする際の判断材料とされます。
- 暴行、脅迫、暴言など、相手の心や身体に悪い影響を与えるような言動や悪口、裁判所に対する濫用的な訴えなど。(※)
- 子どもと別に住む親が、子どもと一緒に住んでいる親の育て方に干渉すること。
- 両親の一方が、特別な理由もないのにもう一方の親に無断で子どもを連れ去ること。
- 親子交流(面会交流)の取り決めがされているのに、子どもと一緒に住んでいる親が理由もなく、子どもと別に住む親との交流を妨げること
※裁判所に対する濫用的な訴え:子どものことを考えるフリをして、実は元パートナーを困らせたいだけの裁判を何度も起こすような行為
親権
【今までどうだった】
これまでは、離婚したら「どちらか一方の親」が親権を持つ、単独親権というルールでした。
実際には、子どもと一緒に暮らす側の親(多くは母親)が親権者になるケースが多く見られました。
【今回どうなった】
「親権は、子どもが安心して成長していけるように、ちゃんと子どものためにつかわなければならない」という考えが、法律の中に明確に書かれるようになりました。
それにより、離婚後でも「両方の親で親権を持つこと(共同親権)」が選べるようになりました。
単独親権か共同親権かを決めるときはは、基本は両親での話し合いですが、決まらない場合は家庭裁判所が決めます。
ただし、子どもへの虐待やDV(家庭内暴力)の心配がある場合や、両親間の話し合いがどうしても難しいような場合は、共同親権にはできません。
そうしたときは、裁判所が判断して「どちらか一方だけが親権を持つ」と決められることになります。
また、基本は「両親で話し合って決めること」が求められますが、日常的なこと(習い事や病院など)は、一方の親だけで判断してよい、というルールもできました。
【なぜ変わったのか】
子どもが安心して安定した環境で育っていけるようにするには、両親が必要に応じて協力しながら育てていく選択肢もあった方がいい、という考えからです。
「子どもが安心して成長するため」に必要な場合、以下のことも認められるようになりました。
- 15歳以上の子どもが「親権をどっちの親にしてほしいか」を家庭裁判所に伝えて、変更をお願いすること(申し立て)
※これは以前からできたことですが、今回の改正で“子どもの声がより大切にされる”仕組みとして、はっきりと位置づけられるようになりました。 - 単独親権から共同親権へ、または共同親権から単独親権へ変更すること
- 両親が結婚していない場合でも、父親が認知した子どもについては共同親権とすること
- 両親の間で意見が対立した場合、家庭裁判所が意見対立を解決するための手続き(調停や審判)
養育費
【今までどうだった】
養育費については、これまで両親の話し合いに任されていて、決めないまま離婚する人も少なくありませんでした。
そのため、あとからトラブルになったり、支払ってもらえなくなるケースも多く見られました。
【今回どうなった】
また、養育費には「先取特権(せんしゅとっけん)」という優先的に差し押さえができる権利が新たにつけられました。
これにより、公正証書がなくても、養育費の取り決めを書面で残していれば、裁判所に手続きをお願いして直接差し押さえをすることもできるようになりました。
【なぜ変わったのか】
子どもへの経済的なサポートが、途中で止まってしまわないようにするためです。
養育費は、子どもの生活や教育にとってとても大切なお金なので、「払われないままになってしまう」ということを減らすために、大きな見直しがされたんです。
※これは、これまでにない画期的な制度です!
- 養育費の支払いがスムーズに進むよう、手続きも見直されました。
- 債務者(払う側)の財産調査と給与差し押さえが、1回の申し立てでできるようになり、「ワンストップ化」が進みました。
- 裁判の中では、家庭裁判所が当事者の収入情報の開示を命じることもできるようになり、正しい金額での養育費の取り決めがしやすくなりました。
最後に少しだけ、注意点
- この法律は2024年5月に成立しましたが、実際に施行されるのは2026年5月ごろの予定です。
今すぐすべての内容が適用されるわけではないことにご注意ください。 - また、すでに離婚した方でも、家庭裁判所に申し立てをすることで、親権の変更(単独親権から共同親権など)が認められる可能性があります。
気になる場合は、専門家に相談してみてくださいね。
この改正では、他にも親子交流や財産分与なども見直されています。
続きは次の記事でご紹介しますね。
⇒離婚後の子の養育に関する民法改正 2024年5月成立②