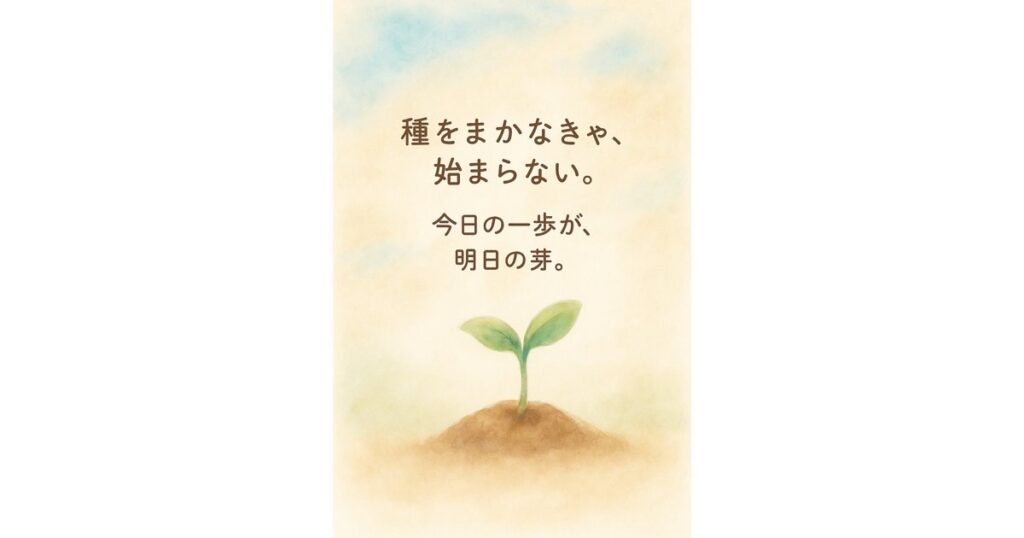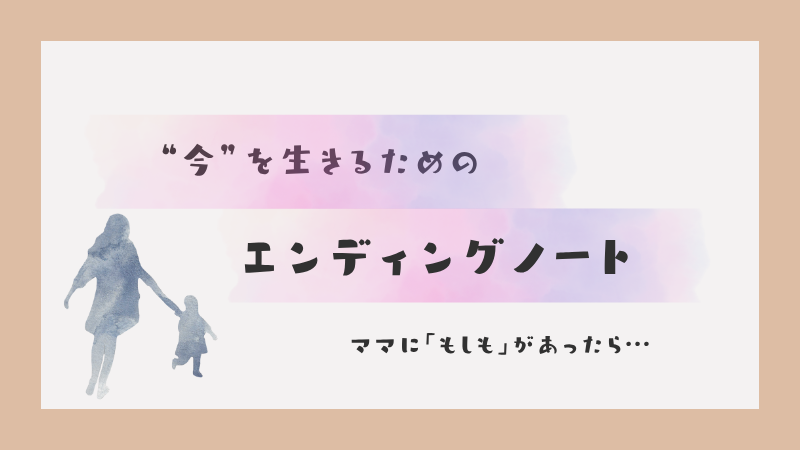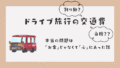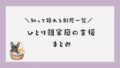「エンディングノート」と聞くと、なんとなく終活と結びついて「年配の方が書くもの」「自分(現役世代)にはまだ早い」と思う人も多いと思います。
「なにを書くの?」「内容が難しそう…」など、内容がよくわからず、興味を持てない人もいるかもしれません。
でも「もしも」は決して他人事ではありません。

ちょっと重たいイメージがあるかもしれませんが、未来の自分や大切な子ども、家族への“優しさ”や“穏やかな暮らしを守る準備”と考えてみてください。
私はひとり親になった今だからこそ、エンディングノートを書きたいと思いました。
結婚していた頃は、「もしも」に備えて保険には入っていたけれど、「結婚している安心感」からか実は現実味を感じていませんでした。
(過去の自分よ、「結婚している安心感」ってなによ?)
今は、子どもを想って、親兄弟を想って、書いておくことで「もしも」のときの周りの人への負担を少しでも減らせるのではないか、と思っています。
エンディングノートは年齢などに関係なく、大切な人の負担を減らして自分の思いを伝えるためにもぜひ書いて欲しいと思います。
エンディングノートって何?遺言書との違いとは?
エンディングノートとは、自分になにかあったときのために、家族や大切な人に伝えたい情報や希望を書いておくノートです。
「医療行為について」「財産について」などの他にも「大切に思っているもの・こと」や「自分の身の回りのこと」も書いておけます。
エンディングノートがあることで、緊急で医療行為が必要なときや亡くなった場合の葬儀・財産の処分などを家族が行うときに、自分の気持を知ってもらうのに大変役に立ちます。
遺言書とは違う?財産や想いを自由に残せるエンディングノート
結論から言うと、エンディングノートと遺言書は別のものです。
遺言書は「自分が亡くなったあとの財産について書き残す、法律的に守られる約束を書面にしたもの」
エンディングノートは「自分が亡くなったあとにして欲しい希望やその手段を書いたお手紙」
というイメージです。
【遺言書とエンディングノートの違い】
項目 | 遺言書 | エンディングノート |
| 法的効力 | あり(要ルール) | なし(自由記入) |
| 内容 | 相続や財産の分配など | 生活や思い、日常のことまで自由に書ける |
| 書き方 | 厳密な形式あり | どんなノートでもOK |
どんなことを書くの?
エンディングノートは遺言書と違って法的効力はありませんが、家族があなたの気持ちを知るうえでとても参考になる大切なものです。
「シングルマザーなのに、死んでしまったら」|エンディングノートを書こうと思ったきっかけ
私は40代のひとり親で、気持ちを伝えておけるパートナーはいません(今後できる予定もありません)。
70代の母が住む実家の近くで、子どもと元保護犬のおばあちゃん犬と生活していて、近所には姉の家もあります。
生活自体はギリギリながら一人でやっていけていますが、「もしも」が起こったときは家族の手を借りることになります。
その場合、少しでも家族が考えなければいけないことや負担を減らしたいと思いました。
そして、子どもの心配が大きかったこと、医療行為について自分の希望があったこと、このことからエンディングノートを書こうと思いました。
子どもに“決断”をさせたくない|大叔母の入院と死から学んだこと
私の大叔母(都会住み・独身・持ち家と遺産あり)が入院・他界したときの話。
母方の大叔母が入院したとの連絡が入ったときは、「延命処置などの治療方針については誰が病院側と話をするのか」を親族会議。
亡くなったときは、「そもそも何をどれだけ持っているのかわからない」「持っていたものはどうするのか」など財産について親族会議。
雪国から都会に出るだけで、後期高齢者の母にとってそこそこ負担でした。
さらには、あれこれ決めなければいけないことがあって、聞いているだけでしんどくなりました。(母よ、よく頑張った。)
正直なところ、私自身は元気が取り柄で入院や死についての現実味は、ほぼゼロでした。
でも、大叔母の話を聞いたことで、生きているうちに自分の意思を書き留めて(できれば伝えて)おくことは、残された子どもや周りへの負担を減らすことになると実感しました。
もちろん、母にもエンディングノートを書くことをすすめました。
子どもへの思い|親権、そして子どもの生活と心
我が家の場合は、私に「もしも」のことがあった場合、子どもはお父さんのもとへ行くことになると思います。
子どもをとても可愛がっていて、子どものために生きているような人なので、子どものために残したお金は子どものために使ってくれると思います。
でも、遠方に住んでいるので「もしも」があれば、子どもの生活環境はガラッと変わってしまいます。
私がいなくなって、お友達とも離れて、いくらお父さんと上の子がそばにいても、ものすごく心細い思いをするでしょう。
だから、新しい環境になっても心を強く持っていけるように、「ママがどれだけ自分のことを想っていたのか」が伝わるように、お金のことだけでなく、たくさんの「だいすき」と「大切」の気持ちを込めたお手紙も残すことにしました。
制度を使うという選択肢もあります。
我が家はお父さんに任せることになると思いますが、中には「子どもの親権を元夫(元妻)に託すの任せるのが不安」「親戚には頼めない」そんな気持ちを持っている方もいると思います。
そんなときに検討できる制度もあります。
子どもが未成年のうちに、親が信頼できる人を”未成年後見人”として遺言などで指名しておける制度です。
未成年の子どもの親が亡くなった場合に、裁判所に任せるのではなく、親自身が「この人に託したい」と意思表示しておくことで、子どもの生活や財産を任せることができます。
未成年後見人とは?:親が亡くなったときに、子どもの生活や財産を守るために選ばれる人のこと。
公正証書で“契約”として後見人を指定できる制度です。
子どもだけでなく、「認知症が不安」「手続きが難しくなったときに頼れる人が欲しい」…など、将来の自分自身のサポートをしてもらう準備にも利用できます。
生命保険の受取人を「信頼できる第三者(他人)」にして、「子どもの学費だけに使ってほしい」など、お金の使い道を指定できるしくみです。
難しい制度の名前だけを聞くと身構えてしまいますが、大切なのは「この人に任せたい」「こうして欲しい」という想いを残しておくことができるということです。
子どもにとって安心できる環境を準備しておくために、知っておいて損はない制度ばかりです。
気になる方は、ぜひ一度調べてみてください。
延命治療の判断|命の選択を託したくない
きっと、命に関わる処置の判断が必要になったとき、家族は延命治療を希望すると思います。
私自身、自分の大切な人がそんな状態になったら「生きていて欲しい」と願って、延命治療を希望すると思います。
でも、私自身は「延命治療は希望しない」と決めていて、家族にもそう伝えてきました。
臓器提供意思表示カードの存在を知ったときから「脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。」を選んで、今も免許証の裏面で意思表示をしています。
これは、家族に辛い判断を任せたくないと思っていたからです。
とくに、ずっと二人で生きてきた子どもには、その重荷を背負わせたくないと強く思っています。
誤解しないでほしいのは、延命治療をする・しないに正解や不正解があるわけではないということです。
「家族の誰かが決断を迫られる前に、自分で準備できることはしておきたい。」
私は、そう思ってエンディングノートに自分の気持ちを残すことにしました。
エンディングノートを書く時間は、「自分と向き合う時間」でした。
実際に書いてみて、いくつか感じたことがありました。
子どもの存在が、どれだけ自分を頑張らせてくれているのか
子どもへの気持ちを言葉にしようとすると、愛しさと寂しさが込み上げてきて、思わず涙がでてきました。
「今、こうして一緒にいられる幸せ」を改めて実感できた瞬間でした。
かつて「お母さん失格だ」と泣いていたときには考えられなかった、穏やかな日々の“当たり前”がすごく尊く思えたんです。
大切な人への“想い”は、飾らず素直に書けばいい
文章を書くことは好きだけど、最初は気持ちがまとまらなくてうまく書けませんでした。
だから、誰かに見せるためじゃなく、「大切な人への想い」を自分の言葉で書くことにしました。
バカの一つ覚えみたいに「だいすき」をたくさん書いた手紙になったけれど、それでも子どもにはちゃんと伝わるだろうと思います。
書くことが、自分のこれからの暮らしを見直すきっかけになる
「このままでいいのかな?」と、未来の自分とも話すような、そんな静かな時間でした。
今の暮らしに向き合うことができて、前向きレベルが少し上がった気がします。
一度書いて終わりではなく、たまに読み返してみるのも大切かも
エンディングノートは「今」の想いを書いたもの。
だからこそ、子どもの成長や自分の考えの変化に合わせて、少しずつ書き直していけると、よりその時の気持ちが伝わる気がします。
エンディングノートの選び方と買い方
いろいろと書いてきましたが、ここまで読んで「ちょっと書いてみようかな」と気になった方は、まず実際にエンディングノートを手に取ってみるのもおすすめです。
実は、エンディングノートは案外身近なところで手に入ります。
情報量と項目がしっかりしてて、「もしも」準備する用として使いやすそう。 |
名前どおり初心者にも優しい設計。書き方ガイドもついてたり、見た目も読みやすい。 |
私が気になったエンディングノートをいくつかピックアップしてみました。価格や内容の違いを比較して、自分に合うものを選んでみてくださいね。
※価格や在庫状況は記事執筆時点のもので、変更される場合があります。購入前にリンク先で最新情報をご確認ください。
エンディングノートって本当に必要なの??
もしかしたら、ここまで読んで「やっぱり私には必要ないかも」と思った方もいるかもしれません。
エンディングノートが「必要かどうか」は人それぞれです。
ただ、「もしも」が起きたときに何も情報がわからないと、残された家族はものすごく多くの時間と労力を使うことになります。
例えば、金融機関の口座情報や各種契約内容など、慎重な性格の方だと、全てのものが必ずしも見つかるとは限りません。
また、命に関わる治療の判断やお葬式の希望は、特に本人の意志を一番に考えたいと思う人が多いのではないでしょうか。
最後に|未来の不安を、少しだけやわらげるために
離婚してシングルマザーになった私の「幸せのハードル」は、とてもとても低くなりました。
結婚していた頃は周りの目が気になって「家族で楽しまなくちゃ」「ちゃんとお母さんしなきゃ」「いい奥さんでいなきゃ」と思っていました。
そして、それができない自分が大嫌いでした。
でも今は「〇〇しなきゃ」が減ったおかげで、穏やかな気持ちでいられることが増えました。
特別なことはなくても、子どもたちと笑っている毎日に幸せを感じています。
そして、元保護犬の愛犬が甘えてくると、「少しは穏やかな犬生を感じてくれているのかな」と、愛しさとともに、そこでも幸せを感じます。
人に振り回されてきた過去がある子でも、最期のときに「人間も悪くなかったな」と思ってもらえたら…そんな気持ちで迎えた子なので、愛犬の笑顔も、私にとってかけがえのない幸せです。

正直お金の余裕はなくて、不安もまだまだあります。
それでも、子どもたちと笑って過ごせる毎日が、私を笑顔で生かしてくれています。
まだまだ、子どもたちと一緒にいたい。
ずっと一緒に笑っていたい。
でも、「もしも」はいつ起こるかわかりません。
エンディングノートは、書き直せないものではありません。
- ふと伝えたいことが出たときに書いてみる
- 口座情報や保険の契約内容など、書けるところから書いてみる
全部を完璧に書こうとせず、かけるところからで大丈夫です。
私たちひとり親にとって、「もしも」はどこかで覚悟しておかないといけない現実的なテーマ。
それに「ちゃんと向き合うこと」が、今を安心して生きることにもつながると、私は思いました。
「いつか」ではなく、「今日の一歩」として、「自分に何かあったとき、これだけは伝えたい」と思うことから書き始めてみませんか?