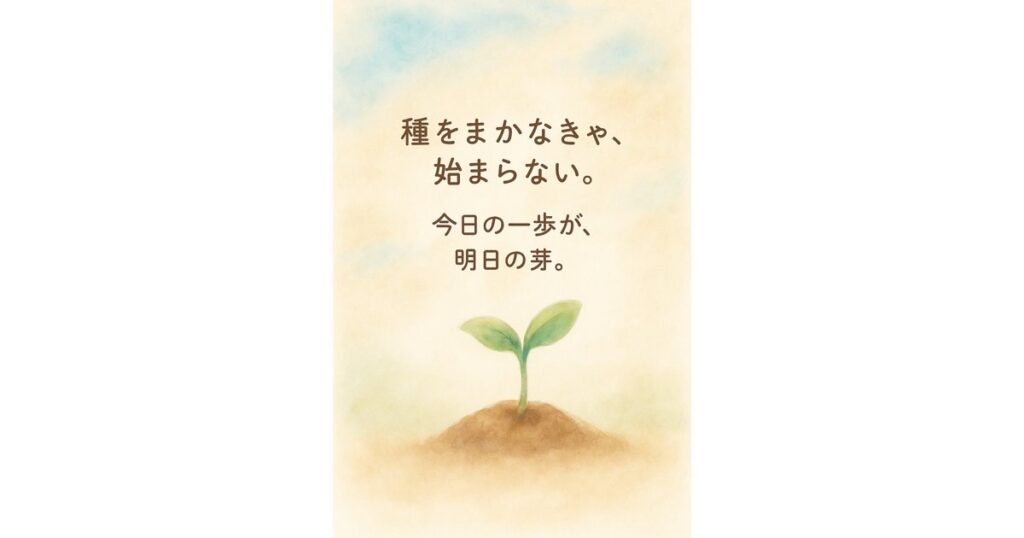ひとり親家庭を支えるために「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の4つの柱で、さまざまなサポートが行われています。
今回は3つ目の「養育費の確保策」について説明します。
養育費の確保策にはどんなものがあるの?
養育費をきちんと受け取れるようにするために、取り決めや支払いの支援だけでなく、親子交流や相談体制の整備、自治体どうしの協力など、いろんな取り組みが行われています。
養育費の確保策:離婚後の金銭的責任・親子交流
- 養育費相談支援センター事業
- 離婚前後支援事業
- 親子交流支援事業
※これらは、国の方針に基づいてつくられた仕組みですが、実施しているかどうかや内容の詳しさは、お住まいの自治体によって違いがあります。
お住まいの市区町村のホームページや相談窓口などで確認してみてください.
1. 養育費相談支援センター事業
この事業は、養育費に関する専門的な相談を受けられる場所として、2007年(平成19年)にスタートしました。
こんな人が使えます。
養育費について、不安や困りごとを抱える人
たとえば:
・養育費の取り決めをしたいけど話が進まない
・支払いが止まってしまって困っている
・そもそも、何から始めればいいのか分からない
そんなときに、専門の相談員が、取り決めや手続きの流れ、必要なサポートについて一緒に考えてくれます。
夜間や休日の相談にも対応しているため、仕事や育児で忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。
実際の相談内容はどんなものがあるの?
令和4年度のデータによると、こんな相談が多く寄せられています。
・「養育費をどう請求すればいいの?」……25.7%
・「いくらが妥当なのか知りたい」……19.0%
・「親子交流のルールって決めた方がいいの?」……17.3%
また、相談の約6割は離婚後に寄せられていますが、離婚前の相談も3割以上あります。
離婚を考え始めている段階でも利用されていることがわかります。
「専門の人に話を聞いてもらえる場所がある」と知っているだけで、気持ちが少しラクになることもあると思います。
2. 離婚前後支援事業
この事業は、離婚前後の時期の悩みを抱える親をサポートしてくれます。
こんな人が使えます。
離婚をする人・離婚をした人
たとえば:
・子どもへの影響を考えながら、養育費や親子交流の取り決めを進めたい
・離婚後の生活のことも、しっかり考えておきたい
・書類や手続きが複雑なので自分だけでは難しい…
そんなときに、必要な情報をわかりやすく教えてもらえたり、気になることを相談できたり、手続きのサポートを受けられたりします。
実際の支援内容にはどんなものがあるの?
・養育費や親子交流の大切さについて学ぶ講座や支援についての情報提供
・離婚を考えはじめたタイミングから相談できる、早めのサポート体制
・養育費の話し合いや手続きに使う書類をそろえるお手伝い
・書類の作成や手続きを進めるための費用の補助
・弁護士などによる個別の相談や費用の補助
・養育費をきちんと受け取るための仕組みづくりの支援
離婚前の「これからどうしよう」にも、離婚後の「困った…」にも寄り添ってくれる制度です。
一人で悩まず、必要なときに頼れる制度のひとつとして、心にとめておいてもらえたらと思います。
3. 親子交流支援事業
離れて暮らす親が「会いたい」と希望して、一緒に暮らす親も「会わせてもいい」と思ったときに、スムーズで安心できる親子交流を行うためのサポートです。
こんな人が使えます。
子どもの親で、親子交流を希望している方
※この制度は、両親ともに「会いたい・会わせたい」と思っている場合に使えます。
たとえば:
・子どもと離れて暮らす親と、子どもを会わせたいけど不安がある
・親子交流の場に、第三者が立ち会ってくれると安心
・交流の方法や頻度を、専門家と一緒に考えたい
そんなときに、相談から親子交流当日の引き渡し・付き添い・交流場所の手配を行ってくれます。
ただし、どちらか一方が「子どものために交流をしたい」と思っても、もう一方の親の同意が得られない場合には、この制度は利用できない決まりになっています。
実際の支援内容にはどんなものがあるの?
・どんなふうに交流していくか、事前に相談して一緒にプランを立てます。
・月1回を目安に、1年間、子どもの引き渡しや付き添いをサポート
・必要に応じて、交流の場所を探すお手伝いもしてくれます。
・子どもが戸惑ったり不安にならないよう、その場のやり取りにもやさしく気を配ってもらえます。
令和4年度には、全国で546件の相談・99件の交流支援が実施されました。
親子関係を無理なく続けるための、やさしい支援のかたちです。
子どもの安心と成長のために必要なもの
養育費と親子交流は、どちらか片方だけではなく、どちらも子どもの安心や成長にとって大切なものです。
実際に、養育費の取り決めがきちんとされている家庭ほど、親子交流も行われている傾向があるそうです。
まるで「車の両輪」のように、どちらもバランスよく支えることで、子どもが安心して育っていける環境が整っていくということですね。
経済的な不安を少しでも減らして、親子のつながりを守りながら、子どもが安心して育っていけるように——そんな想いが、これらの制度には込められています。