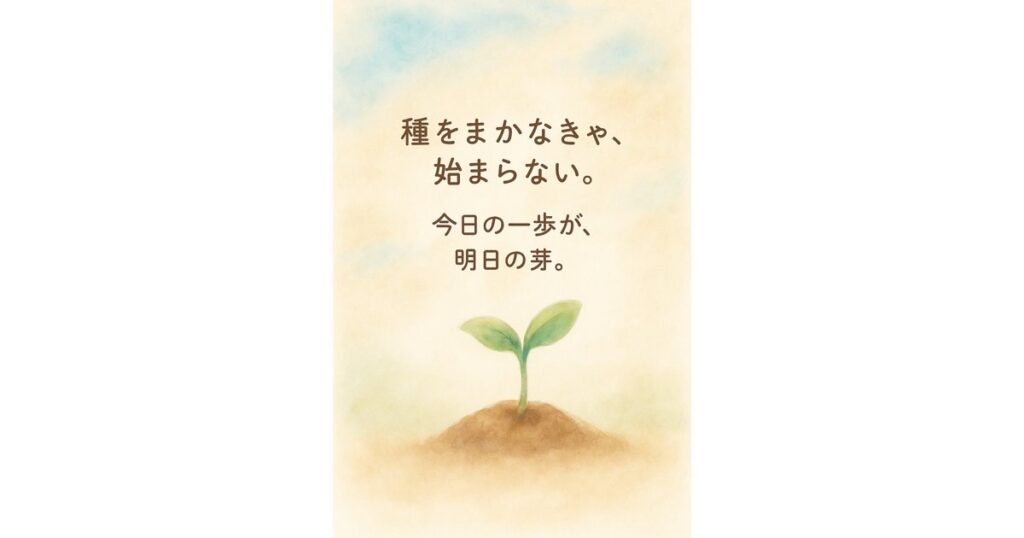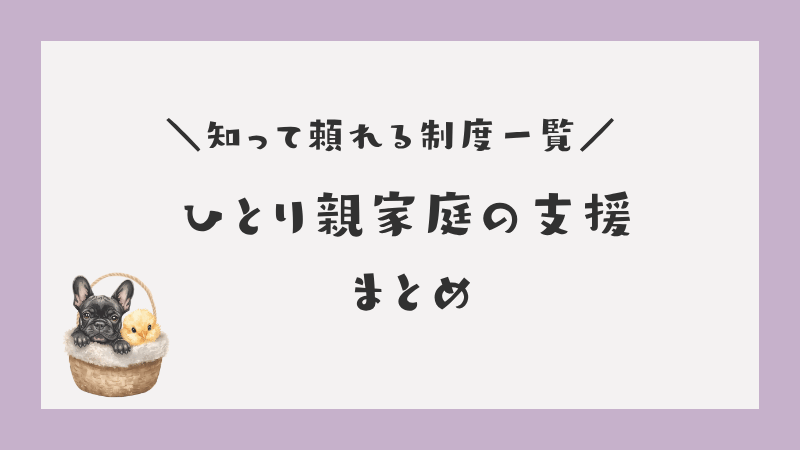小学生になった我が子は、一人でできることも増えて、お手伝いもしてくれる子になりました。
余裕がない日ももちろんありますが、毎日バタバタしていても幸せを感じることも多い日々です。
でも、子どもたちがまだ小さくて手がかかっていた頃は、一人で抱え込んで「今日をどう乗り切るか」で精一杯でした。
子どもの癇癪やぐずりが続いたときは、大人二人で子どもの相手をしていても手が足りない!と思ったこともありました。
子どもと過ごす幸せよりも、家族でいることの辛さの方が強かったあの頃のことは、今も忘れられません。
(その辛さを理解してもらえなかったことも離婚を選んだ理由の1つ…)
今は子どもが成長したことで減った大変さもありますが、ひとり親になったことで「すべてを一人で背負って働く不安」もあります。
きっとまだお子さんに手がかかっているひとり親のお父さん、お母さんの中には、私の想像以上に頑張っている人も少なくないはず。
そんな方が、一人で抱えすぎず、頼るところは頼れるようにひとり親家庭を支える支援策をまとめました。
まだ作成途中で、詳細を紹介しているページがないものもありますが、よかったら「知識の引き出し」に、この一覧を入れておいてもらえたら嬉しいです。
ひとり親家庭を支える4つの支援策とは?
ひとり親家庭を支える支援策を整理すると、主に「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の4つに整理できます。
1.子育て・生活支援策
暮らしや育児をサポートしてくれる制度
1-1.困ったときに相談できる|母子・父子自立支援員による相談支援
1-2.家事や育児を手伝ってもらえる|ひとり親家庭等日常生活支援事業
1-3.学習支援や情報交換で仲間とつながる|ひとり親家庭等生活向上事業
1-4.住む場所を支援|母子生活支援施設・住宅支援資金貸付制度
1-5.地域での子育てを応援|地域こどもの生活支援強化事業
1-6.医療費の負担を減らす|こども医療費助成・ひとり親家族等医療費助成制度
2.就業支援策
働きたい方が仕事につく・学び直すのをサポートをしてくれる制度
2-1.仕事を探したい|マザーズハローワーク事業・就業自立支援事業
2-2.働きながら支援を受けられる|自立支援プログラム策定事業
2-3.スキルアップや資格取得を応援|教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金
2-4.高校卒業程度認定試験をサポート|高卒認定支援事業
2-5.企業も応援してくれてる|ひとり親雇用企業への表彰制度
3.養育費の確保策
離婚後の子どもの生活を守る制度
3-1.養育費の取り決めを支援|養育費相談支援センター事業
3-2.離婚前後の不安をサポート|離婚前後支援事業
3-3.親子関係を保つ|親子交流支援事業
4.経済的支援策
生活費や教育費など、お金の負担を減らすための制度
4-1.毎月もらえるお金|児童扶養手当
4-2.学費や生活資金が借りられる|母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
4-3.家賃をサポート|ひとり親家庭住宅手当(家賃補助)※
4-4.自治体ごとの手当もチェック|児童育成手当※
4-5.税金が安くなる|ひとり親控除(必要なら)※
※4-3.
住宅手当の内容や名称(住宅手当/家賃補助/住宅費助成制度など)は都道府県や市区町村によって異なります。また、市区町村によっては市営住宅・県営住宅などへの入居申込の支援としている場合もあります。お住まいの地域の役所へ確認してみてください。
※4-4.
「児童育成手当」は東京都など一部の自治体で実施されている制度です。実施されているか・支給内容・名称などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの市区町村にご確認ください。
※4-5.
「ひとり親控除」は、扶養している子どもがいるひとり親の方が対象で、寡婦控除・寡夫控除とは条件が異なります。
詳しくは国税庁の所得控除に関する案内ページも参考にしてください。(寡婦控除の説明ページに飛びます。ひとり親控除はページ下の「関連コード」の項目から)
最後に
ひとりで頑張り続けるのは、本当に大変なことです。
だからこそ、使える支援を知って、頼って、少しでも穏やかな気持ちで過ごせる毎日につながるといいな、と思います。