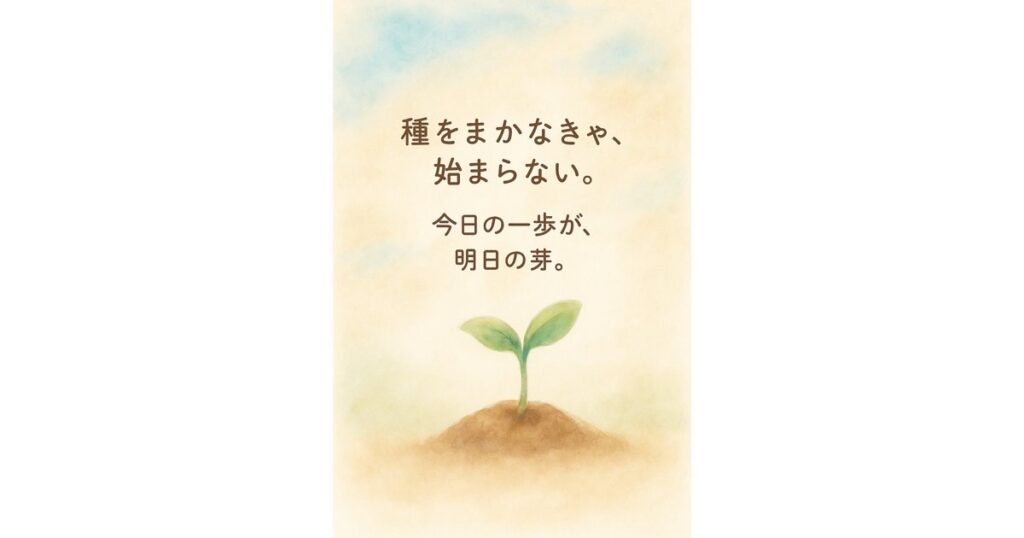離婚は多くの人にとって人生を左右する大きな決断で、離婚すべきかどうかは誰にも答えが出せません。
でも「今じゃない」というタイミングはあります。
この記事では、まだ離婚する段階ではないかもしれない人の特徴について、感情面・経済面・家族(特に子ども)への影響の3つの視点をお伝えします。
【ポイント①】離婚を考えると泣けてくる場合
たとえそれが愛情ではなく「情」からくる涙だとしても、「辛い」「悲しい」「寂しい」「わかって欲しい」といった感情が湧き上がるうちは、まだ相手への気持ちが残っていると思います。
心の中にある「本当は別れたくない」「やり直したい」という本音に気づいたら、相手に打ち明けて話し合うことで、関係が変化する可能性もあります。
夫婦が話し合えるうちは、まだお互いに相手に関心があると思うので、腹を割って話してみてください。
話し合えない相手になってしまったなら、きっとそのうち涙が出なくなる日がきます。
徐々にその日に向けて地盤を固めていきましょう。
【視点②】離婚後の生活が今より苦しくなることが予想される場合
離婚当初は「別れてよかった」と感じても、時間が過ぎて経済的な不安や不満が出てきたときに「愛情はなくなっていたけれど、別れなくてもよかったんじゃないか」と後悔するケースも少なくないようです。
専業主婦で収入がない場合や、働いていても自分だけの収入では不安がある人は早まってはいけません。
感情に任せて離婚して、「生活が苦しくなった」「離婚しなければよかった」とならないように、まず離婚後の収入と支出を具体的に出してみてください。
生活レベルが明らかにダウンすることが予想される場合は、「今」ではありません。
経済的に損な関係なら続ける必要はないと思いますが、経済的メリットが残っていれば今することは「一旦保留+地盤固め(経済力をつける)」です。
【視点③】子どもや親兄弟が悲しんで、関係に悪影響を残す可能性がある場合
子どもが離婚に納得していない場合や、離婚によって親に大きな負担をかけてしまうことが予想される場合は、すぐに離婚を決断するのではなく、一度立ち止まって考えてみることも大切です。
自分の感情や都合を優先しすぎると、あとから「親子関係がぎくしゃくしてしまった」「罪悪感が残った」と悩むこともあります。
離婚が“穏やかに生きるための選択”であっても、それによって大切な人との関係が壊れてしまうと、本末転倒になってしまうかもしれません。
そうならないためにも、夫婦間だけでなく、子どもや親にもきちんと気持ちを伝え、納得してもらえるような話し合いを重ねることが大切です。
とはいえ、「両親が揃っているのが一番いい」という考えに、無理に縛られる必要もないと思っています。
私は、「しかめっ面の両親が一緒にいるより、片親でも穏やかな暮らしの方が子どもにとっても幸せなんじゃないか」と思い、そう正直に伝えました。
これらのケースでは、衝動的な離婚ではなく、関係修復の可能性や、離婚後の影響を深く考える必要があると思います。
ただし、激しい夫婦喧嘩が絶えない、DV・モラハラがあるなど、夫婦関係を続けていることが子どもに怖い思いをさせることになる場合は、子どもの心身のために前向きに離婚を検討してほしいと思います。
私の場合ですが、夫は年齢が少し離れていたこともあって、恋人のころから私のことをとても大切にしてくれていました。
しかし、夫婦の間に少しずつ溜まった互いの不満が、私を彼の”大切な相手”ではなくしてしまいました。(今なら反省できる)
話し合いをしてもわかってもらえず、わかってもらえない話し合いに疲れて、離婚を考え始めた頃は「辛い」「悲しい」「寂しい」という感情ばかりでした。
それでも次第に話し合いができない関係に諦めがついて、経済面で離婚後の生活も想像できるようになったことで、最終的には気持ちにけじめをつけ、離婚を選びました。
離婚・保留・再構築、どれが正解かはわかりません。
「もうダメだ」と思うときほど、少しだけ立ち止まって、自分の中の本音を見つめてみてください。
「今じゃない」と思ったら結論を焦らず、あなたのペースであなたの答えを見つければいい。
どれを選んでも、「自分で選んだ」と言える選択なら、それが正解だと思います。
私自身、8割は「この選択(離婚)でよかった」と思えていますが、離婚から3年経った今も「これでよかったのかな」と思う日はあります。